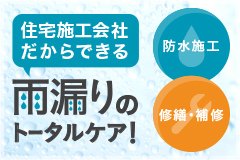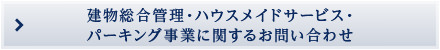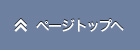雨漏りというと、屋根の不備で起こるイメージが強いと思います。
しかし、実際には屋根以外の箇所からもいくつも雨漏りが発生しています。
その一つが「窓サッシ周りからの雨漏り」です。
窓サッシ周りからの雨漏りの原因は、主に雨仕舞や出窓の不具合によるものです。
屋根や外装に問題がないのに雨漏りが発生してしまう場合は、窓サッシ周りからの可能性が高いです。
普段雨が当たらない窓サッシ周りの接合箇所に、台風や豪雨などが起きた際に影響を受けてしまうことがあります。
天災害の後には何かしらの不都合が起きてしまうお宅は、一度点検をすることを強くお勧めします。
日栄商工は専門家がしっかりと点検、修理を行います。
お気軽にご相談ください。
近年は昔と違い、気候の変化が年々激しくなってきています。
異常気象の発生も年々増えてきているのが現状です。
そんな環境の変化に伴い、雨漏り事情も変化してきています。
近年、多くなってきた事例として以下の2つあります。
①異常気象で雨水が吹き上がることで軒天の隙間から入り込む
②太陽光パネルの設置による下地の破損
昔に比べて雨漏り発生原因が多様化しているのが最近の傾向です。
そうなると、住まい全体を把握している業者でなければ点検が行き届かないことがでてきます。
日栄商工では住まいのトータルケアを行っている会社です。
住まいの専門業者として対応させていただきます。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
雨漏りの直接的な原因、4つ目は「“谷樋”の雨仕舞いの不備」です。
“谷樋”とは、瓦屋根同士をくっつける際に施工されるものです。
瓦同士はぴったりくっつけることができないので、そのすき間を埋めるために谷樋を施工します。
谷樋は金属で施工するので、長年の雨による浸食や最近の酸性雨の影響により穴が開いてしまうことがあります。
そして、その穴が原因で雨漏りが起こります。
金属でも同じ場所に何年も水滴が当たることで穴が開いてきてしまいます。
屋根の部分でも、特に意識して点検しなければ気がつけない部分です。
定期的な点検には、ぜひ雨漏り修理の専門家「日栄商工」にご相談ください。
雨漏りの直接的な原因、3つ目は「“漆喰(しっくい)”の崩れ」です。
“漆喰”は、昔は「石灰」と表記されていたものです。。
水酸化カルシウム・炭酸カルシウムを主成分としており、
土壁よりも雨や風に強く、防水性があります。
不燃素材のため、外部保護材料として、古くから城郭や寺社、商家、民家、土蔵など、
木や土で造られた壁に用いられてきた建築素材です。
また漆喰は、瓦止めとしても使われることも多いですが、
雨風にさらされ続けて崩れてしまう場合があります。
その崩れた部分から雨漏りが発生することがあります。
実際に専門家の目で確認しなければ、どの程度の崩れなのかという判断も難しいです。
ぜひ屋根の点検には日栄商工へご連絡ください。
専門の社員がご自宅へ伺わせていただきます。
雨漏りの直接的な原因、2つ目は「“スレート”のひび割れ・浮き」です。
“スレート”とは、粘土版岩を薄く加工した板状の屋根材です。
スレートの種類も豊富にあります。
・天然スレート:天然の原石を使用した、高級感のあるスレート
・石綿スレート:セメントと石綿(アスベスト)を混ぜたスレート
・無石綿スレート:アスベストの問題から、石綿スレートの代わりとして開発されたスレート
・セメント系スレート:セメントを主材としたプレート
このスレートが雨風にさらされて、ひび割れが起こったり、浮き上がったりしてしまうことがあります。
そうやってできたすき間から雨漏りが起こります。
普段見えない箇所の点検などは、ぜひ専門家にご相談ください。
雨漏りの直接的な原因の多くは、大きく分けて6つのいずれかに当てはまります。
まず1つ目に、「屋根の“練板金”の浮き」によるものです。
練板金とはストレート屋根の頂点を止めている鉄板のことを言います。
マンションなどとは違い、一軒家に多い“三角屋根”の瓦などを止めるために使われます。
屋根の最後の「しまい」と表現されることもあります。
この“練板金”の箇所は風圧が強く掛る場所です。
そのため、釘が浮いたり抜けたりして釘穴から水が入り、中の木が腐ってしまう場合があります。
古いタイプの棟板金には、錆が生じてしまうものもあります。
練板金を古いタイプから新しいものに換えるだけでも、建物の印象はガラッと変わります。
屋根の上は住まいの中でも日常的に目の届かない場所です。
普段見えない部分の点検は、ぜひ専門家にご相談ください。
以前から雨漏りの原因である腐朽菌が多いとされる床下環境を紹介してきました。
ではなぜ床下の湿度は高いのか理由をご説明します。
①床下の地面からの水分の蒸発
②冬季の上部の建物側との境界に発生する結露
(冬は室内側の床が暖かいため、地面側に水蒸気がたまる)
③床下換気口などから浸入する水分
(床下換気口の位置が低く雨水が流入など)
④床下を通る給排水管からの漏水
主に、上記の4点があげられます。
これらの問題への対策としては、床下換気や防湿コンクリートの打設、べた基礎の採用などがあります。
日栄商工では、直接お客様のご自宅にお伺いし状況を把握した上で工事内容を決定します。
まずはお気づきの点がございましたらご相談ください。
雨漏りで被害の大きい床下の環境についてご説明します。
実際に、床下の環境とはどういったものなのでしょうか。
床下は空気の入れ替えが難しい、密閉された空間です。
床下の換気が不十分であるために湿気が高くなり、床下の木材の含水率が上がります。
含水率が高くなると、腐朽菌が繁殖し、土台に使われた木材が腐ってきます。
そうすると、強度が低下し、住まいそのものの強度が失われてしまいます。
住まいを長持ちさせるためにも、床下の換気はとても重要です。
※キッチンや洗面所、浴室などの水回り部分の床下は、特に湿気が溜まりやすい傾向にあります。
そのため、床下の中でも特にカビや腐朽菌が繁殖しやすくなるので、注意が必要です。
何かご不安な点や気になることがございましたらお気軽にご相談ください。
日栄商工では経験豊富な専門社員が対応させていただきます。
以前ご紹介した、家を腐らせてしまう腐朽菌の対策として重要なのが湿気対策です。
腐朽菌の繁殖条件は、酸素と温度が関わってきますが、この2つを制御するのはとても困難です。
さらに最終的には、水か養分を絶たなければならないため、
実際の対策としては、「木材を乾燥した状態に保つこと」、また「防腐剤による処理」が最も有効です。
酸素と温度の関係からも、床底は地上に近く湿気も吸いやすい状態にあるので、最も腐りやすい部分になります。
見えない床下の箇所でも、日栄商工では専門家が現場へ伺わせていただき点検をいたします。
ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
「雨漏りの問題」は、アパートやマンションのトラブルの原因になることがあります。
下記のようなトラブルが起きています。
・雨漏りで家具などの生活用品が破損してしまう
・壁や床にカビが生える
・フローリングが湿気で曲がってしまい隙間ができてしまう
・漏電でブレーカーが上がらない
雨漏り修理の費用は、家主の負担となりますが、破損した私物に関しては、保障がされない場合も多くあるようです。
家主様はもちろん、住居者様もなにか気になる箇所や不安なことがございましたら、早い段階でのご連絡をオススメいたします。